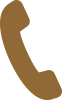2025.08.08
コラム
下肢静脈瘤治療で「失敗した」と後悔しないために!再発・合併症を避ける賢い選択と対策

はじめに
下肢静脈瘤治療で「失敗した」と感じるあなたへ
下肢静脈瘤の治療を検討している、あるいはすでに治療を受けたものの、「もしかして失敗だったのかも…」と不安や後悔を感じていませんか?
足の血管が浮き出てくる下肢静脈瘤は、見た目の問題だけでなく、足のだるさ、むくみ、痛み、こむら返りといった不快な症状を引き起こします。
これらの症状から解放されたいと願い、治療に踏み切ったにもかかわらず、期待通りの結果が得られなかったり、予期せぬ問題に直面したりすると、大きな落胆や不安を感じるのは当然のことです。
多くの人が抱える不安と後悔
・「治療したのに症状が改善しない」
・「手術後に再発してしまった」
・「術後の痛みが続く」
・「色素沈着が残ってしまった」など
下肢静脈瘤の治療に関する「失敗談」は、インターネット上でも散見されます。
これらの情報に触れると、「自分も同じような経験をするのではないか」という不安に駆られたり、実際に「失敗した」と感じている方は「なぜ自分だけがこんな目に…」と孤独を感じたりすることもあるでしょう。
しかし、ご安心ください。下肢静脈瘤の治療は、その性質上、いくつかのリスクや予期せぬ経過をたどることがあり、あなたが感じている不安や後悔は、決して珍しいことではありません。
この記事で伝えたいこと
この記事では、あなたが抱えるであろう、治療への不安や後悔に真摯に向き合います。
なぜ「失敗」と感じるケースが起こるのか、その主な原因を具体的に解説し、そうした状況を避けるための賢い病院(クリニック)・医師選びのポイント、そして再発や合併症を最小限に抑えるための対策を詳しくご紹介します。
さらに、もし「失敗した」と感じてしまった場合に、諦めずに取るべき行動についても触れていきます。
この記事が、あなたの下肢静脈瘤治療に対する理解を深め、後悔のない選択をするための一助となることを心から願っています。
下肢静脈瘤治療で「失敗」と感じる主なケースと原因
下肢静脈瘤の治療は、多くの場合、症状の改善や美容的な効果をもたらしますが、中には「失敗した」と感じてしまうケースも存在します。
これらの「失敗」は、必ずしも医療ミスを意味するわけではなく、治療の特性、患者さんの体質、術後のケアなど、様々な要因が絡み合って生じることがあります。
ここでは、一般的に「失敗」と感じられやすい主なケースと、その背景にある原因について詳しく見ていきましょう。
ケース1:治療後に症状が改善しない・悪化した
治療を受けたにもかかわらず、足のだるさ、むくみ、痛み、こむら返りといった下肢静脈瘤特有の症状が改善しなかったり、むしろ悪化したりするケースです。
これは、患者さんにとって最も「失敗」と感じやすい状況の一つでしょう。
原因:診断ミス、不適切な治療法の選択、術後のケア不足など
- 診断ミスや不適切な治療法の選択: 下肢静脈瘤と診断されても、その原因が本当に静脈瘤にあるのか、あるいは他の疾患(例えば、腰椎疾患や他の血管疾患)が症状の原因となっている可能性もあります。正確な診断が行われず、症状の原因ではない静脈瘤だけを治療しても、根本的な症状改善には繋がりません。また、患者さんの静脈瘤の状態やライフスタイルに合わない治療法が選択された場合も、期待する効果が得られないことがあります。
- 術後のケア不足: 治療法によっては、術後の適切な圧迫療法(弾性ストッキングの着用など)や、日常生活での注意(長時間の立ち仕事や座りっぱなしを避けるなど)が非常に重要です。これらのケアが不十分だと、治療効果が十分に発揮されなかったり、症状が再燃したりする可能性があります。
- 深部静脈の機能不全: 下肢静脈瘤は、皮膚に近い表在静脈の問題が原因であることが多いですが、足の血液の大部分を心臓に戻す役割を担う深部静脈に問題がある場合もあります。深部静脈の機能不全が症状の主な原因であるにもかかわらず、表在静脈の治療だけを行っても、症状の改善は限定的となることがあります。
ケース2:治療後に再発してしまった
一度治療したにもかかわらず、再び静脈瘤が浮き出てきたり、症状が再燃したりするケースです。これは、患者さんにとって精神的な負担も大きい「失敗」と感じる要因となります。
原因:治療範囲の不足、新たな静脈瘤の発生、体質など
- 治療範囲の不足: 治療時に問題のある静脈をすべて処理しきれていなかった場合、残存した静脈から静脈瘤が再発することがあります。特に、複雑な静脈の走行を持つ場合や、複数の静脈に問題がある場合に見られます。
- 新たな静脈瘤の発生: 治療した静脈とは別の静脈に、新たに静脈瘤が発生することもあります。下肢静脈瘤は進行性の疾患であり、治療後も加齢や生活習慣、遺伝的要因などにより、新たな静脈瘤が発生するリスクはゼロではありません。
- 体質や生活習慣: 遺伝的な要因や、長時間の立ち仕事、妊娠、肥満など、下肢静脈瘤になりやすい体質や生活習慣が改善されない場合、再発のリスクが高まります。
- 治療法の選択: 硬化療法など、一部の治療法は他の治療法に比べて再発率がやや高いとされています。治療法選択の際に、再発のリスクについても十分に説明を受け、理解しておくことが重要です。
ケース3:治療後に合併症(痛み、色素沈着、神経障害など)が残った
治療自体は成功したものの、術後に予期せぬ合併症や後遺症が残り、それが患者さんの生活の質を低下させるケースです。これもまた、「失敗」と感じる大きな要因となります。
原因:術中の偶発症、術後の管理不足など
- 術後疼痛: 治療法によっては、術後に一時的な痛みや違和感が続くことがあります。これは通常、時間とともに軽減しますが、痛みが長引いたり、予想以上に強かったりすると、患者さんは「失敗」と感じるかもしれません。特に、レーザー治療や高周波治療では、熱による組織の損傷が痛みの原因となることがあります。
- 色素沈着: 治療した静脈の周囲に、茶色っぽい色素沈着が残ることがあります。これは、治療によって破壊された赤血球のヘモグロビンが皮膚に沈着することで起こり、特に硬化療法後に見られることがあります。時間の経過とともに薄くなることが多いですが、完全に消えない場合もあります。
- 神経障害: 治療部位の近くを通る神経が、治療中に損傷を受けることで、しびれや感覚の異常、痛みが残ることがあります。これは比較的稀な合併症ですが、患者さんの生活に大きな影響を与える可能性があります。
- 深部静脈血栓症: 非常に稀ですが、治療後に深部静脈に血栓ができることがあります。これは重篤な合併症であり、肺塞栓症を引き起こす可能性もあるため、早期の診断と治療が必要です。
- 感染症: 手術部位の感染症も稀に発生することがあります。適切な消毒や術後の管理が行われていればリスクは低いですが、発症すると治療の遅延や追加治療が必要となります。
ケース4:期待した美容効果が得られなかった
下肢静脈瘤の治療は、症状改善だけでなく、見た目の改善を目的とする場合も少なくありません。しかし、治療後に期待したほど見た目が改善しなかったり、逆に新たな血管が目立つようになったりすると、「失敗」と感じることがあります。
原因:術前の説明不足、患者の期待値とのギャップなど
- 術前の説明不足と期待値のギャップ: 治療によってどの程度の美容効果が得られるのか、術前に医師から十分な説明がなかったり、患者さん自身の期待値が現実と乖離していたりする場合に起こりやすいです。特に、細いクモの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤は、治療が難しい場合や、治療後も完全に消えないことがあります。
- 新たな血管の出現: 治療後に、治療部位の周囲に新たな細い血管(マット状血管拡張症など)が出現することがあります。これは、治療による炎症反応や血流の変化が原因と考えられており、患者さんにとっては「治療したのに悪くなった」と感じる要因となります。
これらの「失敗」と感じるケースは、治療を受ける前に十分な情報収集を行い、医師と密にコミュニケーションを取ることで、ある程度は回避したり、その影響を最小限に抑えたりすることが可能です。
次のセクションでは、そうした「失敗」を避けるための賢い病院・医師選びのポイントについて解説します。
「失敗」を避けるための賢い病院(クリニック)・医師選びのポイント
下肢静脈瘤治療における「失敗」を未然に防ぎ、後悔のない結果を得るためには、治療を受ける病院(クリニック)や医師を慎重に選ぶことが非常に重要です。
適切な医療機関を選ぶことで、正確な診断、最適な治療法の選択、そして術後の適切なケアが期待できます。
ここでは、賢い病院(クリニック)・医師選びのためのポイントをいくつかご紹介します。
保険診療の基本とクオリティの差
下肢静脈瘤の治療は、多くの場合、健康保険が適用される「保険診療」の対象となります。
これは、国が定めた診療報酬点数に基づいて治療費が計算されるため、どの医療機関で治療を受けても、基本的な料金は全国で一律であるという原則を意味します。
患者さんは自己負担割合(1割、2割、3割など)に応じて費用を支払うことになります。
しかし、ここに大きな落とし穴があります。
料金が全国一律であるからといって、提供される治療のクオリティや、それによって得られる効果までが同じであるとは限りません。むしろ、その逆であると認識すべきです。
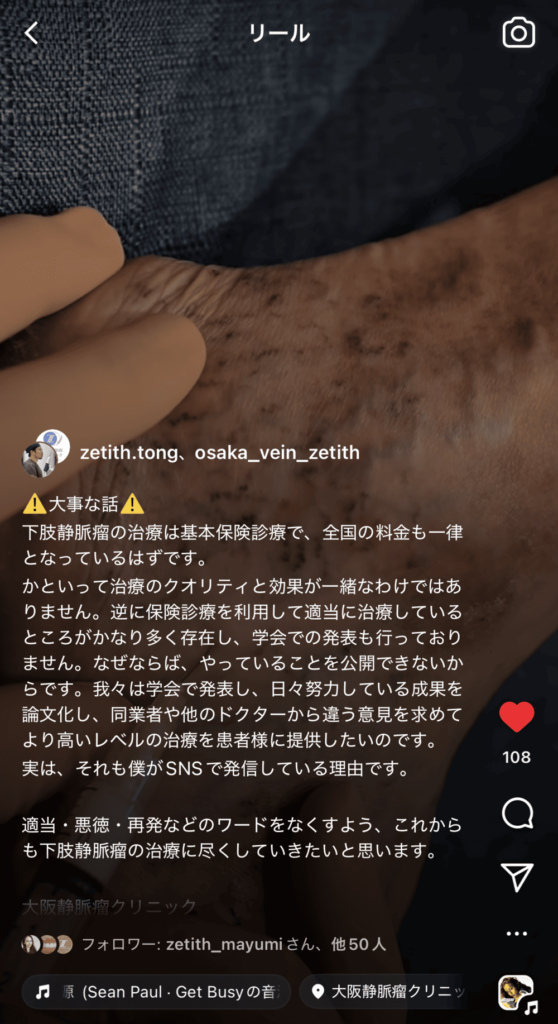
大事な話
(大阪静脈瘤クリニック 佟医師のSNSより)
「下肢静脈瘤の治療は基本保険診療で、全国の料金も一律となっています。しかし、だからといって治療のクオリティと効果が一緒なわけではありません。むしろ、保険診療を利用していい加減に治療しているところがかなり多く存在し、学会での発表も行っていません。なぜならば、やっていることを公開できないからです。私たちは学会で発表し、日々努力している成果を論文化し、同業者や他のドクターから違う意見を求めて、より高いレベルの治療を患者様に提供したいのです。」
この「大事な話」が示すように、保険診療の枠内であっても、クリニックや医師によって治療の質には歴然とした差が存在します。
残念ながら、保険診療の仕組みを逆手にとって、十分な技術や経験を持たずに「いい加減に」治療を行っている医療機関も少なくないのが現状です。
医師の経験と資格
下肢静脈瘤の治療は、血管外科や心臓血管外科を専門とする医師が行うのが一般的です。
治療の成功には、医師の豊富な経験と確かな技術が不可欠です。
以下のような実績や資格を持つ医師は、信頼の目安となります。
- 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医: 下肢静脈瘤の主要な治療法である血管内焼灼術を安全かつ正確に行うための資格です。この資格を持つ医師は、十分な技術と経験を積んでいると判断できます。
- 血管内治療の経験: 下肢静脈瘤治療だけでなく、腹部・胸部ステントグラフトなど、より高度な血管内治療の経験も豊富である医師は、複雑な症例にも対応できる可能性が高いでしょう。
- 所属学会: 日本心臓血管外科学会、日本血管外科学会、日本静脈学会など、関連する学会に所属し、最新の知見や技術を常にアップデートしているかも重要なポイントです。
治療実績と医療設備
治療実績(症例数)は、その医療機関や医師が様々なケースに対応できる経験の豊富さを示す重要な指標です。
年間どのくらいの症例数を扱っているかを確認することも重要です。
症例数が多いほど、多様な状況に対応できる経験が豊富であると考えられます。
また、最新の超音波診断装置など、充実した医療設備が整っているかも確認しましょう。精度の高い診断と治療には、適切な設備が不可欠です。
Google口コミやSNSでの評判も参考に
Google口コミやSNSでの評判も、病院選びの一つの参考になります。
実際にそのクリニックや医師に診てもらった患者さんの生の声は、ホームページやパンフレットには書かれていない、よりリアルな情報を得る上で役立ちます。
ただし、口コミは個人の主観が大きく反映されるため、全てを鵜呑みにせず、あくまで参考情報として活用することが大切です。
特に、多くの患者さんが共通して言及している点(例:医師やスタッフの対応が丁寧、説明が分かりやすい、待ち時間が長いなど)に注目すると良いでしょう。
また、悪い口コミだけでなく、良い口コミにも目を通し、総合的な判断材料とすることをおすすめします。

丁寧な説明とコミュニケーション
医師が治療のメリットやリスクについて、患者さんが納得できるまで丁寧に説明してくれるかどうかも、病院(クリニック)選びの重要なポイントです。
十分に時間を取って話し合い、不安や疑問を解消できる医療機関を選びましょう。
十分なインフォームドコンセントを通じて、患者さん自身が納得して治療を選択できる環境が整っていることが、後悔のない治療につながります。
丁寧なカウンセリングと説明(インフォームドコンセントの徹底)
治療を受ける前に、医師から十分な説明を受け、納得した上で治療に臨む「インフォームドコンセント」は非常に重要です。以下の点に注目しましょう。
- 診断の根拠: なぜその診断に至ったのか、エコー検査などの画像を見せながら丁寧に説明してくれるか。
- 治療法の選択肢: あなたの静脈瘤の状態やライフスタイルに合わせた複数の治療法を提示し、それぞれのメリット・デメリット、費用、治療期間、術後の経過、そしてリスクや合併症について、分かりやすく説明してくれるか。
- 質問への対応: あなたの疑問や不安に対して、時間をかけて丁寧に答えてくれるか。質問しにくい雰囲気ではないか。
- 治療のゴール設定: 治療によってどの程度の改善が見込めるのか、現実的なゴールを共有してくれるか。特に美容的な効果については、過度な期待を抱かせない説明が重要です。
複数の治療法の選択肢とメリット・デメリットの説明
下肢静脈瘤の治療法は一つではありません。
レーザー治療、高周波治療、硬化療法、ストリッピング手術、グルー治療など、様々な方法があります。
それぞれの治療法には、得意な静脈瘤の種類や、術後の回復期間、費用、そしてリスクが異なります。
一つの治療法しか提案しない医師や医療機関は、その治療法しかできない、あるいはその治療法に固執している可能性があります。
あなたの状態に最適な治療法を提案してくれるか、複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリットを公平に説明してくれる医師を選びましょう。
術後のフォローアップ体制の充実
治療は、手術が終われば全てが完了するわけではありません。
術後の経過観察や、万が一の合併症、再発時の対応など、長期的なフォローアップ体制が整っているかを確認しましょう。
- 定期的な診察: 術後、どのくらいの頻度で、いつまで定期的な診察が必要か。
- 緊急時の対応: 術後に痛みや腫れ、発熱などの異常があった場合に、どのように対応してくれるのか、連絡体制は整っているか。
- 再発時の対応: 万が一再発した場合に、どのような治療オプションがあるのか、費用はどうなるのかなど、事前に説明があるか。
セカンドオピニオンの活用
もし、医師の説明に疑問を感じたり、提示された治療法に不安があったりする場合は、迷わずセカンドオピニオンを検討しましょう。
セカンドオピニオンとは、現在の主治医以外の医師に、診断や治療方針について意見を聞くことです。
複数の医師の意見を聞くことで、より客観的な情報を得ることができ、納得して治療を選択するための助けとなります。
セカンドオピニオンを快く受け入れてくれる医師は、患者さんの意思を尊重し、自信を持って治療にあたっている証拠とも言えるでしょう。
これらのポイントを踏まえ、焦らず、複数の医療機関を比較検討し、あなた自身が「この医師なら信頼できる」「この病院なら安心して任せられる」と感じられる場所を選ぶことが、「失敗」を避けるための最も重要なステップとなります。
下肢静脈瘤の再発・合併症を最小限に抑えるための対策
下肢静脈瘤治療における「失敗」を避けるためには、適切な病院・医師選びだけでなく、治療法ごとのリスクを理解し、術後の適切なケアと日常生活での注意点を守ることが不可欠です。
ここでは、再発や合併症を最小限に抑えるための具体的な対策について解説します。
治療法ごとのリスクと対策
下肢静脈瘤の治療法は多岐にわたり、それぞれに特徴とリスクがあります。ご自身の選択した、あるいは検討している治療法について、改めてリスクと対策を確認しましょう。
レーザー治療・高周波治療
これらの血管内焼灼術は、低侵襲で回復が早いのが特徴ですが、熱を用いるため、術後に痛みや内出血、色素沈着、神経損傷のリスクがあります。
- 対策: 術後の適切な圧迫(弾性ストッキング)は、内出血や腫れを抑え、色素沈着のリスクを軽減します。また、術後の早期歩行は血栓予防に繋がります。神経損傷は稀ですが、治療部位の神経走行を熟知した医師による正確な手技が重要です。
硬化療法
薬剤を注入して静脈を閉塞させる治療法で、比較的軽度な静脈瘤や、他の治療後の残存静脈瘤に用いられます。色素沈着や血栓性静脈炎のリスクがあります。
- 対策: 術後の圧迫と歩行は必須です。色素沈着は時間とともに薄れることが多いですが、完全に消えない場合もあります。血栓性静脈炎は、痛みや硬結を伴いますが、通常は数週間で改善します。医師の指示に従い、適切な処置を受けることが大切です。
ストリッピング手術
問題のある静脈を物理的に引き抜く手術で、根治性が高いとされます。他の治療法に比べて侵襲が大きく、術後の痛み、内出血、神経損傷、深部静脈血栓症のリスクがやや高まります。
- 対策: 術後の痛みに対しては、適切な鎮痛剤の使用や冷却が有効です。深部静脈血栓症予防のため、術後の早期離床と歩行、弾性ストッキングの着用が重要です。神経損傷を避けるためには、熟練した外科医による手技が求められます。
グルー治療
医療用接着剤(グルー)で静脈を閉塞させる比較的新しい治療法です。熱を使わないため、神経損傷のリスクが低いとされますが、接着剤によるアレルギー反応や、稀に血栓性静脈炎のリスクがあります。
- 対策: アレルギー反応の既往がある場合は、事前に医師に伝える必要があります。術後の圧迫は不要とされることが多いですが、医師の指示に従いましょう。新しい治療法であるため、長期的なデータが蓄積されている専門施設での治療が望ましいです。
術後の適切なケアと日常生活の注意点
どの治療法を選択した場合でも、術後の適切なケアと日常生活での注意点を守ることは、再発や合併症を防ぎ、治療効果を維持するために非常に重要です。
弾性ストッキングの着用
医師から指示された期間、適切に弾性ストッキングを着用しましょう。弾性ストッキングは、足に適度な圧力をかけ、血液の逆流を防ぎ、むくみを軽減し、血栓予防にも役立ちます。特に術後は、内出血や腫れを抑える効果も期待できます。
適度な運動と休息
術後は、医師の指示に従って早期に歩行を開始し、適度な運動を心がけましょう。ウォーキングは、ふくらはぎの筋肉ポンプ作用を促し、血流改善に繋がります。長時間同じ姿勢でいることを避け、適度に休憩を取り、足を動かすことが大切です。また、十分な休息も回復には不可欠です。
長時間同じ姿勢を避ける
立ち仕事や座りっぱなしの仕事が多い方は、定期的に休憩を取り、足首を回したり、ふくらはぎを伸ばしたりする運動を取り入れましょう。これにより、足の血液が滞留するのを防ぎ、静脈への負担を軽減できます。
定期的な診察と経過観察
治療後も、医師の指示に従って定期的に診察を受け、経過を観察してもらいましょう。これにより、万が一再発の兆候や合併症の発生があった場合でも、早期に発見し、適切な対応を取ることができます。症状がなくても、定期的なチェックは非常に重要です。
これらの対策を講じることで、下肢静脈瘤治療後の再発や合併症のリスクを最小限に抑え、より良い治療結果を維持することが可能になります。
もし「失敗した」と感じたら?諦めずに取るべき行動
どれだけ慎重に病院を選び、術後のケアを熱心に行っても、残念ながら「失敗した」と感じてしまう状況に直面することもあるかもしれません。
適切な行動を取ることで、状況を改善し、再び前向きな治療へと繋げることが可能です。
ここでは、もし「失敗した」と感じた場合に取るべき行動について解説します。
まずは主治医に相談する
治療後に症状が改善しない、悪化した、あるいは予期せぬ合併症が出た場合、まず最初に行うべきは、治療を担当した主治医に相談することです。
自分の感じている不安や具体的な症状を、遠慮せずに正直に伝えましょう。
医師は、あなたの訴えを聞き、必要に応じて再検査を行い、現在の状況を評価します。
その上で、追加の治療や対処法を提案してくれるかもしれません。
コミュニケーションを通じて、誤解が解消されたり、新たな解決策が見つかることもあります。
セカンドオピニオンを検討する
主治医との相談で納得のいく回答が得られなかったり、別の視点からの意見も聞きたいと感じたりした場合は、セカンドオピニオンを積極的に検討しましょう。
セカンドオピニオンは、患者さんの権利として認められています。
別の専門医の意見を聞くことで、現在の診断や治療方針が適切であるかを確認したり、新たな治療選択肢を知るきっかけになったりすることがあります。
専門の医療機関を再度受診する
セカンドオピニオンの結果、あるいはご自身の判断で、現在の医療機関では解決が難しいと感じた場合は、下肢静脈瘤治療に特化した別の専門医療機関を受診することも有効な選択肢です。
特に、再発や難治性のケースでは、より高度な知識と経験を持つ専門医の診察が必要となる場合があります。
新たな医療機関では、これまでの治療歴を詳しく伝え、現在の症状や不安を丁寧に説明しましょう。
場合によっては、これまでの治療では対応しきれなかった原因が特定され、より効果的な治療法が提案されることもあります。
精神的なサポートも視野に入れる
治療の「失敗」は、身体的な苦痛だけでなく、精神的なストレスや落胆を伴うことがあります。特に、期待が大きかった分、その反動で精神的に落ち込んでしまうこともあるでしょう。
もし、不安やストレスが日常生活に支障をきたすようであれば、心療内科や精神科の専門医に相談することも検討してください。また、同じような経験を持つ患者さんのコミュニティやサポートグループに参加することで、共感や情報共有を通じて精神的な負担が軽減されることもあります。
「失敗」と感じる状況は辛いものですが、それは決して治療の終わりではありません。
諦めずに適切な行動を取り、信頼できる医療者と共に、あなたの足の健康を取り戻すための道を模索し続けることが大切です。
まとめ
後悔のない下肢静脈瘤治療のために
下肢静脈瘤の治療は、多くの人にとって症状の改善と生活の質の向上をもたらすものです。
しかし、「失敗」という言葉が示すように、治療後の経過は常に順風満帆とは限りません。
再発や合併症、期待通りの効果が得られないといった状況に直面し、不安や後悔を感じることもあるでしょう。
しかし、この記事を通じてお伝えしたかったのは、そうした状況は決して珍しいことではなく、適切な知識と行動によって乗り越えられるということです。
信頼できる情報と専門家との連携が重要
後悔のない下肢静脈瘤治療を実現するためには、まず正確で信頼できる情報を得ることが不可欠です。
インターネット上の情報だけでなく、専門クリニックの医師からの直接的な説明を重視し、疑問点は積極的に質問しましょう。今はSNSのDMなどで質問に答えてくれる医師も増えてきています。
そして、最も重要なのは、あなたの症状や不安に真摯に向き合い、最適な治療法を提案し、術後も長期的にサポートしてくれる信頼できる医師や医療機関を見つけることです。
セカンドオピニオンの活用も、納得のいく選択をするための有効な手段です。
あなたの足の健康を取り戻すために
下肢静脈瘤は、適切な診断と治療、そして術後の継続的なケアによって、症状の改善が期待できる疾患です。
たとえ一度「失敗した」と感じたとしても、諦めずに、この記事で紹介したポイントを参考に、もう一度あなたの足の健康を取り戻すための道を歩み始めてください。
あなたの足が、再び軽やかに、そして自信を持って歩めるようになることを心から願っています。
大阪静脈瘤クリニック
銀座で大人気「Zetith Beauty Clinic」による大阪静脈瘤クリニックが梅田に2021年7月OPEN 院長は血管外科で培った幅広い知識・経験のある佟 暁寧先生。 院長は、完治すれば終わりではなく美しい見た目を最終ゴールとして患者様に寄りそった医療を提供してきました。また、患者様が安心して過ごせるように接遇向上や待ち時間短縮にもできる限り配慮し、そんな患者様ファーストの姿勢が評価され、遠方からもご来院いただくまでになりました。 大阪静脈瘤クリニックも、スタッフ皆で力を合わせて、 ホスピタリティあふれる空間にしていきます。
クリニックでは下肢静脈瘤の専門医が診察、治療を責任をもって行います。 「足の血管が浮き出ている」「足が重くだるい」「足がかゆい」「足がむくむ」「夜、足がつって眠れない」「足の皮膚の色が黒ずんでいる」こういった症状が見られる方は下肢静脈瘤の恐れがあります。入院の必要はなく日帰りで帰れるのはもちろん、痛みも感じないため、治療当日から通常通りの生活が送れます。今まで培った知識や技術のすべてを注ぎこみ、日々の診療にあたっています。足は生活の基礎となる重要な体の一部です。少しでも不調を感じたら、放置せず、ぜひお早めにご相談ください。
また手の甲の血管「ハンドベイン治療」や顔の血管治療「フェイススクレロセラピー」といった血管に特化した佟医師だからこそ対応できる治療もございますので血管のお悩みは当院へご相談ください。
〒530-0057
大阪府大阪市北区曽根崎2-12-4
コフレ梅田8階
06-6130-8852
大阪静脈瘤クリニック公式サイトはこちら

この記事の監修者
院長 佟 暁寧